2019年7月にフルモデルチェンジしてデビューした新型タント(4代目)は、群雄割拠の軽トールワゴンジャンルでライバルとの差別化を図るために、さまざまな新機構を採用しています。
その中のひとつが、新開発されたCVT(クルマに詳しくない人には、オートマの一種と考えていただけると分かりやすいかもですね)です。
クルマに求められる性能はさまざまなものがありますが、燃費性能は重要なポイントのひとつです。
そんな燃費性能は、さまざまな要因で大きく変わりますが、【CVT】は重要部位のひとつです。
新型タントに採用された【D-CVT】は、いわゆる従来のCVTでは限界だった部分を超えた性能を持っていると言います。
 悩める購入者
悩める購入者限界の向こう側?そんなことが可能なの?
どういうことなのか、専門的な知識を持った人向けではなく、クルマに詳しくない方に向けて簡単に解説していきたいと思います。
CVTってなんなの?
クルマはエンジンの動力をまずトランスミッションに伝えて、そののちにタイヤの回転運動へと変換することで走行することが可能です。
このトランスミッションという機械には、内部構造の違いによって、大きく分けて以下の3つのタイプがあります。
- マニュアルトランスミッション(MT)
- オートマチックトランスミッション(AT)
- 無段変速機または連続可変トランスミッション(CVT)
基本的には、MT以外であればAT免許で変わらず運転できるものなので、まとめてATという認識でいる方も多いでしょう。
新型タントに採用されているのはCVTです。
そして、これらのトランスミッションは内部でエンジンからの回転運動を、減速したり増速したりしています。(減速比を変える)
それによって、燃費性能を高めたり、発進時には重いクルマを動かすわけですから、モリモリ力強いパワーをタイヤへと伝えたりしています。
- 小さいギヤで大きいギヤを回すと、エンジンの回転数から減速されることでモリモリパワー!
- 大きいギヤで小さいギヤを回すと、エンジン回転が増速され効率よく少ない力でスピードアップ!
トランスミッションは、このような中学生くらいの物理で習う原理を使用しているわけです。
このシステムはどんなクルマにも必要不可欠なものです。
ATやMTが決められた数のギヤ(歯車) で動力伝達しているのに対して、CVTはベルトを2つあるプーリーのかけ、そのプーリーの幅を拡げたり狭めたりすることで 、ギヤの大⇔小関係と同じ状況をつくり出だしています。
このプーリーの幅は、その特徴から無段階で調整することが可能なので、CVTが無段変速と言われているのはこのためです。
分かりにくい方は、自転車のチェーンとギヤの関係をイメージしていただければわかるでしょう。
自転車の前後のギヤを直接噛み合わせているのが、ATやMTです。
自転車と同じようにチェーンで前後のギヤを繋いでいて、なおかつその繋がっているギヤの大きさが、自在に変化するのがCVTです。
新型タントのCVTは高速域で限界の向こう側へ!

CVTを採用している新型(4代目)タントには、ダイハツの最新のCVT【D-CVT】が採用されています。
基本的にベルト駆動であるCVTに、ギヤを追加したのがこの【D-CVT】の特徴です。
このギヤを使うことこそが、まさに限界突破できるその大きな要因です。
これがなぜそうなるのかを説明するのは、プロの自動車整備士でも簡単なことではないのでここでは割愛します。
簡単にいうと、ベルト駆動によって減速比が変わったものがそのままタイヤに伝わっていたのが従来のCVTです。
 整備士ヒロ
整備士ヒロその間にギヤ機構が入ることで、ベルト駆動後の回転数をさらに変化させて、タイヤに出力を伝えることができるというものなんですね。
高い最終減速比により新型タントは【7~8速ATと同等レベルのポテンシャル】を秘める
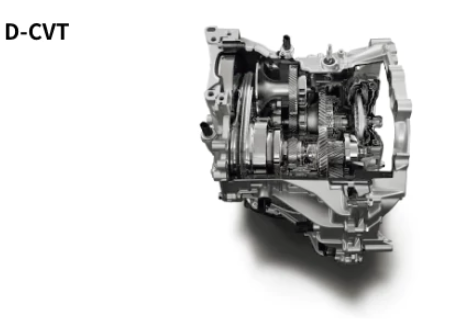
最終減速比がどんな数値なのかのくわしい解説はさておき、この数字が大きければ大きいほど加速するときの力強さは大きくなります。
 悩める購入者
悩める購入者じゃあ、大きくすりゃそれで、いいんじゃないの?
…かというと、そういうわけではありません。
その対価として、高速走行時の燃費性能が落ちることになります。
カンタンにいうと、同じ回転数でタイヤを転がすのに、減速比が大きいほうがエンジン回転数が高くなってしまいます。
※以下は理屈を説明するための簡略的なものです。rpmは1分間当たりの回転数を表します。
| エンジン回転数 (rpm) | 減速比 | 計算の仕方 | 車速 (rpm) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 4 | 2000÷4 | 500 |
| 2000 | 5 | 2000÷5 | 400 |
| 2500 | 5 | 2000÷5 | 400 |
状況によって必ずしもそうではありませんが、エンジン回転数が高いとその分多く燃料も使うので、燃費が悪くなります。
しかし、さきほども解説したように限界の向こう側を実現した新型タントの【D-CVT】は、その優秀な内部機構によって最終減速比を大きく高めることができました。
ちなみに、新型タント(L650S)と旧型タント(L375)を比較するとその数値の違いは歴然です。
| 車種名 | 最終減速比 |
|---|---|
| 新型タント | 6.618 |
| 旧型タント | 5.297 |
これは、多段式のATと同等レベルのポテンシャルです。
例えると、7~8速ATクラスと遜色ありません。
日産のスカイライン等と同等レベルですね!
 整備士ヒロ
整備士ヒロちなみに軽自動車のATと言えば5速ATが一般的なので、新型タントのCVTがいかに優れているのかお分かりいただけるかと思います。
新型タントの【D-CVT】のそのほかの燃費向上のための技術
新型タントの【D-CVT】にはほかにも省燃費性能を高めるための、トピックがあるのでここで代表的なものを2つ紹介しておきましょう。
※FF駆動(2WD)かつ自然吸気エンジン(NA)で比較。ただし、スペーシアはマイルドハイブリッド車。
| 車種名 | WLTCモード燃費 |
|---|---|
| ダイハツ タント | 21.2km/L |
| スズキ スペーシア | 22.2 km/L |
| ホンダ N-BOX | 21.8 km/L |
| 日産 ルークス | 20.8 km/L |
CVTフルードは低燃費性能に優れるものを採用
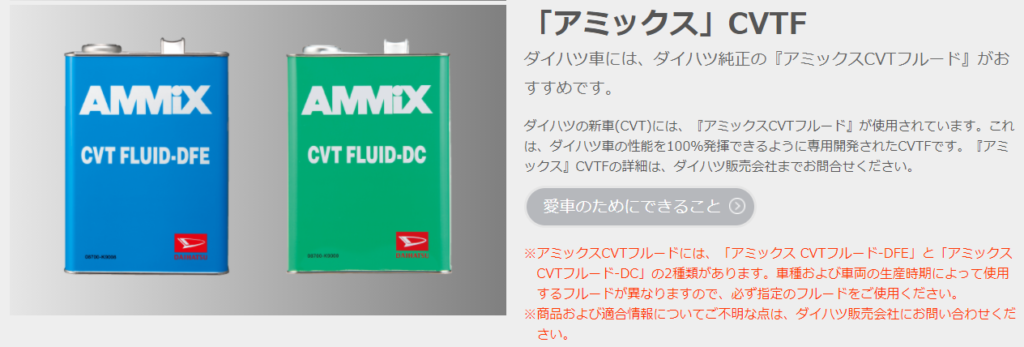
CVTの内部にはフルード(オイル)が入っています。
自動車の部品には、いたるところにオイル(またはフルード)が使用されており、部品を作動させたり、潤滑、冷却などさまざまな役割があります。
よって、かならず適材適所の、専用オイル(フルード)を使用する必要があります。
新型タントには、新開発された【D-CVT】に合わせた『低粘度性能に優れるアミックスCVTフルードDFE』が採用されています。
このCVTフルード自体は目新しいものではありませんが、対応していない古いモデルにこのフルードを入れると壊れる可能性もあるので注意が必要です。
 整備士ヒロ
整備士ヒロ逆にいえば、新型タントの省燃費性能を最大限発揮するためにはダイハツ車専用に開発されている『アミックスCVTフルードDFE』を使用する必要があるということですね。
CVTフルードウォーマーでロスを低減して燃費性能を向上
自動車は冷えているときは、燃費が悪くなります。
自動車はエンジンだけでなく、トランスミッション(AT/CVT)も、良いパフォーマンスを発揮するのは冷えているときよりも暖まっている状態のときです。
冬場に燃費が悪くなるのはそのためです。
よって、エンジンをかけてからは少しでもはやくエンジン・トランスミッションを暖めてあげることが好ましいです。
ちなみにエンジンのほうが トランスミッション(AT/CVT) よりも圧倒的にはやく暖まります。
そんな特性を利用して、新型タントにはCVTフルードウォーマーがついています。
CVTフルードウォーマーとは、エンジンの冷却水を使ってCVTフルードをあたためる装備のことです。
冷えているときはメカロス(機械が駆動するときの抵抗や駆動損失)が大きくなります。(これが燃費が悪くなる原因のひとつですね)
 整備士ヒロ
整備士ヒロよって、CVTフルードウォーマーによって、少しでもはやく暖めてあげることでメカロスを低減し、省燃費性能を高めてあげようということですね!
CVTフルードウォーマーや、低燃費性能に優れたCVTフルードの採用は、いまでは決して珍しくない、どんなクルマでも当たり前となっているものです。
自動車メーカーにはこうしたさまざまな努力があって、自動車は様々な性能を維持・向上しつつ、それと相反する問題が発生したときは、最善のブレークスルーを常に考えて自動車の開発をおこなっているのです。
まとめ
かなり、簡略的な解説となりましたがご理解いただけましたか?
自動車整備士が新機構を勉強するテキストにも紹介されていたのが、新型タントの【D-CVT】です。
よって、業界人も注目する技術であることは間違いありません。
カタログ上の燃費性能ではライバル車種に及ばない部分もありますが、新型タントにはこんな誇れる部分もあるんだと思うと、愛車(タント)への愛着も深まりますよね。




